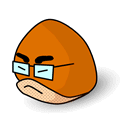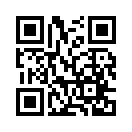2009年01月28日
新・被災地ジオラマ製作(第1回)
このブログで製作過程をお伝えしてきました「被災地ジオラマ」ですが、地元宮城の新聞、河北新報(記事)にも大きく取り上げられ、反響もいただきました。ありがとうございます。
ジオラマの今後の展開については、既にお伝えしているとおり、
1.製作範囲を拡げる。
2.同じ地点の被災前と被災後を作り、比較できるようにする。
という事で、意見は一致しています。
ただ、製作範囲を広げる。つまり別の被災現場をジオラマで再現するという事なんですが、これにも色々と簡単にいかない問題があったりします…
そこで、まずは前回製作した「冷沢」の崩落前の姿をジオラマで再現する事から始めます。
実は、前回のジオラマは、「とりあえず作ってみよう」って感じで始めたものですから、今後の展開というのは全く考えていませんでした。
例えば、別の地点のジオラマを製作し、それらを連結していく事によって、最終的には耕英地区全体をジオラマで再現するという構想(夢)もある中で、前回のジオラマでは整合性に問題が出てくるでしょう。
新しいジオラマはそれらを考慮に入れながら、製作していきたいと思いますが、そうすると新しいジオラマ(被災前)と前回のジオラマ(被災後)でも、若干形が変わってくるので、比較に適さなくなるかもしれません。
まぁ、ひとつ作るのもふたつ作るのもあまり変わらないから、この際、「新規格」で被災前と被災後を同時に製作していきます。
では早速、製作に取り掛かります。
(1)土台となる板(横45センチ×縦30センチ)に、地震で崩壊する前の道路や等高線を転写していきます。
縮尺は約1/2500になりますので、この板の場合、実際のスケールだと縦1125メートル×横750メートルぐらいです。(実際は少し大きく作っています。)

(2)転写した線はわかりやすいように色で区別します。赤は道路、青は沢、黒は計曲線(等高線)です。今回も1/25000地形図をベースにしていますので、地形図同様、等高線を50メートル毎に太めて表現しています。

次回につづく…
▼こちらもよろしくお願いします▼


ジオラマの今後の展開については、既にお伝えしているとおり、
1.製作範囲を拡げる。
2.同じ地点の被災前と被災後を作り、比較できるようにする。
という事で、意見は一致しています。
ただ、製作範囲を広げる。つまり別の被災現場をジオラマで再現するという事なんですが、これにも色々と簡単にいかない問題があったりします…
そこで、まずは前回製作した「冷沢」の崩落前の姿をジオラマで再現する事から始めます。
実は、前回のジオラマは、「とりあえず作ってみよう」って感じで始めたものですから、今後の展開というのは全く考えていませんでした。
例えば、別の地点のジオラマを製作し、それらを連結していく事によって、最終的には耕英地区全体をジオラマで再現するという構想(夢)もある中で、前回のジオラマでは整合性に問題が出てくるでしょう。
新しいジオラマはそれらを考慮に入れながら、製作していきたいと思いますが、そうすると新しいジオラマ(被災前)と前回のジオラマ(被災後)でも、若干形が変わってくるので、比較に適さなくなるかもしれません。
まぁ、ひとつ作るのもふたつ作るのもあまり変わらないから、この際、「新規格」で被災前と被災後を同時に製作していきます。
では早速、製作に取り掛かります。
(1)土台となる板(横45センチ×縦30センチ)に、地震で崩壊する前の道路や等高線を転写していきます。
縮尺は約1/2500になりますので、この板の場合、実際のスケールだと縦1125メートル×横750メートルぐらいです。(実際は少し大きく作っています。)

(2)転写した線はわかりやすいように色で区別します。赤は道路、青は沢、黒は計曲線(等高線)です。今回も1/25000地形図をベースにしていますので、地形図同様、等高線を50メートル毎に太めて表現しています。

次回につづく…
▼こちらもよろしくお願いします▼
2009年01月22日
「風雪とともに 開拓地耕英」を観る(第3回)
前回の続きです。
ちなみに紺色の部分は僕の勝手な補足です。
 『目を付けたのが県北の栗駒である。この地は開拓の余地が十分あると考えたからである。』
『目を付けたのが県北の栗駒である。この地は開拓の余地が十分あると考えたからである。』
なぜか、この映像では触れられていませんが、いきなり栗駒にやってきてしまいます。
まず、八島氏と宮城県庁経済課主事の菅原兵市氏との職務から始まる運命的な出会いがありました。二人は意気投合し満州開拓に意欲を燃やします。兵市氏は県庁を依願退職。自ら団長となり、満州開拓に乗り出します。しかし多くの団員とともに満州で帰らぬ人に…
 『駒の湯温泉の経営者・菅原兵三郎氏に声を掛けたところ、快く引き受けてくれた。駒の湯温泉の発展を期待する彼にとっても、好都合だったに違いない。』
『駒の湯温泉の経営者・菅原兵三郎氏に声を掛けたところ、快く引き受けてくれた。駒の湯温泉の発展を期待する彼にとっても、好都合だったに違いない。』
焼香に訪れた八島氏は兵市氏の父・兵三郎氏と帰国した団員の受け入れについて相談します。兵三郎氏も「満州で死んだせがれや孫たちのためにも、また駒の湯の発展のためにもぜひ実現してください」と八島氏にお願いしたそうです。
 『昭和22年3月31日、駒の湯温泉のいくつかの部屋を無償で借り受け、28名を送り込んだ。この時点で入植許可はまだ下りていなかった。』
『昭和22年3月31日、駒の湯温泉のいくつかの部屋を無償で借り受け、28名を送り込んだ。この時点で入植許可はまだ下りていなかった。』
この時点では駒の湯の一部を除き、ブナの大木に覆われた原生林で、訪れる者といえば夏山登山者と湯治客のみでした。
要するに駒の湯以外に何もない状態だったので、駒の湯に泊まりながら開拓していった。それが駒の湯が「耕英の原点」と言われる所以です。
 『八島氏は土地の開放と入植許可を佐々木家寿治県知事に迫ったが、計画した土地は国有地として、青森営林局古川営林署が所轄していたため、土地に開放に予想外の困難を要した。』
『八島氏は土地の開放と入植許可を佐々木家寿治県知事に迫ったが、計画した土地は国有地として、青森営林局古川営林署が所轄していたため、土地に開放に予想外の困難を要した。』
『営林署では現地の生活は不可能との見解を崩さず、その時点で製炭材として十ヘクタールの払い下げに応じたに過ぎなかった。』
営林署も「あんな所マジで開拓するの!?」とか思っていたんでしょうか。
 『それでも八島氏は土地の解放運動を強力に推し進めた。その結果、翌年の23年4月1日、やっとのことで正式に開拓地として許可が下りた。新しい開拓地が誕生したのである。』
『それでも八島氏は土地の解放運動を強力に推し進めた。その結果、翌年の23年4月1日、やっとのことで正式に開拓地として許可が下りた。新しい開拓地が誕生したのである。』
 『満州耕野開拓団より、さらに秀でた開拓地にしようとの願いから、秀を「英」とし、耕野の一字「耕」を取って、この開拓地を「耕英(こうえい)」と名付け、耕英開拓農業共同組合を発足させた。』
『満州耕野開拓団より、さらに秀でた開拓地にしようとの願いから、秀を「英」とし、耕野の一字「耕」を取って、この開拓地を「耕英(こうえい)」と名付け、耕英開拓農業共同組合を発足させた。』
2008年7月9日付の読売新聞の記事によると“一説に耕英は、「耕す英雄」の意。”と紹介されています。これはどうかな…
『しかし、開拓地として許可された喜びは束の間で、厳しい自然条件と食料難や道が不便なため、この地を離れる者が続出した。』
次回に続く…
▼こちらもよろしくお願いします▼


ちなみに紺色の部分は僕の勝手な補足です。
 『目を付けたのが県北の栗駒である。この地は開拓の余地が十分あると考えたからである。』
『目を付けたのが県北の栗駒である。この地は開拓の余地が十分あると考えたからである。』なぜか、この映像では触れられていませんが、いきなり栗駒にやってきてしまいます。
まず、八島氏と宮城県庁経済課主事の菅原兵市氏との職務から始まる運命的な出会いがありました。二人は意気投合し満州開拓に意欲を燃やします。兵市氏は県庁を依願退職。自ら団長となり、満州開拓に乗り出します。しかし多くの団員とともに満州で帰らぬ人に…
 『駒の湯温泉の経営者・菅原兵三郎氏に声を掛けたところ、快く引き受けてくれた。駒の湯温泉の発展を期待する彼にとっても、好都合だったに違いない。』
『駒の湯温泉の経営者・菅原兵三郎氏に声を掛けたところ、快く引き受けてくれた。駒の湯温泉の発展を期待する彼にとっても、好都合だったに違いない。』焼香に訪れた八島氏は兵市氏の父・兵三郎氏と帰国した団員の受け入れについて相談します。兵三郎氏も「満州で死んだせがれや孫たちのためにも、また駒の湯の発展のためにもぜひ実現してください」と八島氏にお願いしたそうです。
 『昭和22年3月31日、駒の湯温泉のいくつかの部屋を無償で借り受け、28名を送り込んだ。この時点で入植許可はまだ下りていなかった。』
『昭和22年3月31日、駒の湯温泉のいくつかの部屋を無償で借り受け、28名を送り込んだ。この時点で入植許可はまだ下りていなかった。』この時点では駒の湯の一部を除き、ブナの大木に覆われた原生林で、訪れる者といえば夏山登山者と湯治客のみでした。
要するに駒の湯以外に何もない状態だったので、駒の湯に泊まりながら開拓していった。それが駒の湯が「耕英の原点」と言われる所以です。
 『八島氏は土地の開放と入植許可を佐々木家寿治県知事に迫ったが、計画した土地は国有地として、青森営林局古川営林署が所轄していたため、土地に開放に予想外の困難を要した。』
『八島氏は土地の開放と入植許可を佐々木家寿治県知事に迫ったが、計画した土地は国有地として、青森営林局古川営林署が所轄していたため、土地に開放に予想外の困難を要した。』『営林署では現地の生活は不可能との見解を崩さず、その時点で製炭材として十ヘクタールの払い下げに応じたに過ぎなかった。』
営林署も「あんな所マジで開拓するの!?」とか思っていたんでしょうか。
 『それでも八島氏は土地の解放運動を強力に推し進めた。その結果、翌年の23年4月1日、やっとのことで正式に開拓地として許可が下りた。新しい開拓地が誕生したのである。』
『それでも八島氏は土地の解放運動を強力に推し進めた。その結果、翌年の23年4月1日、やっとのことで正式に開拓地として許可が下りた。新しい開拓地が誕生したのである。』 『満州耕野開拓団より、さらに秀でた開拓地にしようとの願いから、秀を「英」とし、耕野の一字「耕」を取って、この開拓地を「耕英(こうえい)」と名付け、耕英開拓農業共同組合を発足させた。』
『満州耕野開拓団より、さらに秀でた開拓地にしようとの願いから、秀を「英」とし、耕野の一字「耕」を取って、この開拓地を「耕英(こうえい)」と名付け、耕英開拓農業共同組合を発足させた。』2008年7月9日付の読売新聞の記事によると“一説に耕英は、「耕す英雄」の意。”と紹介されています。これはどうかな…
『しかし、開拓地として許可された喜びは束の間で、厳しい自然条件と食料難や道が不便なため、この地を離れる者が続出した。』
次回に続く…
▼こちらもよろしくお願いします▼
2009年01月20日
「風雪とともに 開拓地耕英」を観る(第2回)
前回の続きです。
ちなみに紺色の部分は僕の勝手な補足です。
 『耕野(こうや)村とは、現在の伊具郡丸森町耕野である。』
『耕野(こうや)村とは、現在の伊具郡丸森町耕野である。』
耕野に親戚がいるんで、以前行った事があります。阿武隈川と山に挟まれた風光明媚な所です。タケノコが美味しかったですね。
 『当時の耕野村の村長の任にあった八島考二氏は、狭い耕野村から満州への分村を考えていた。』
『当時の耕野村の村長の任にあった八島考二氏は、狭い耕野村から満州への分村を考えていた。』
満州へ移民は人口増加や農地不足等の諸問題を解決しようとする政府の国策によって強力に推進されました。
村を分けるような形で集団移民する「分村」が耕野村でも計画されました。
 『なぜならこの地域には三反百姓が多く、次男、三男の働き口がなく、一家でも食うに足りないという有様だったからである。』
『なぜならこの地域には三反百姓が多く、次男、三男の働き口がなく、一家でも食うに足りないという有様だったからである。』
まさにウチの母方の祖父はこの耕野村出身で次男でした。そして、満州開拓にも行きました。
 『満州へ移民団を送るには、団長の資格を有した者が必要であるなど、問題も多かったが、何とか解決を図り、次々と満州へ開拓団を送り出した。』
『満州へ移民団を送るには、団長の資格を有した者が必要であるなど、問題も多かったが、何とか解決を図り、次々と満州へ開拓団を送り出した。』
団長になるのには幹部訓練を受ける必要がありました。昭和15年、耕野村より第一次開拓団20名が先遣隊として渡満。17年に栗原郡文字村(現栗原市)の14名と一緒に第二次開拓団が渡満。この時の団長は駒の湯温泉の経営者・菅原兵三郎氏を父に持つ菅原兵市氏でした。
 『開拓団の戸数も百戸を超えた。』
『開拓団の戸数も百戸を超えた。』
満州は食べ物が豊富だったらしいです。しかも満州では、満州人が開墾した所にそのまま入植し、開墾するのでもトラクターなど機械が使えたようです。
 『しかし、昭和20年敗戦となり、それとともに第二の故郷を捨て、帰国せざる負えなくなってしまった。ところが、帰国はしたものの行き場所がなかった。』
『しかし、昭和20年敗戦となり、それとともに第二の故郷を捨て、帰国せざる負えなくなってしまった。ところが、帰国はしたものの行き場所がなかった。』
ソ連の突然の侵攻により、命からがら日本に戻ってきます。その途中で多くの団員を失います。
映像では触れられていませんが、実際に引揚げ時の体験談を聞くと涙が止まりません。
 『その団員を耕野村だけで収容しきれなかったのである。そこで八島考二氏の私有地を開放し入植させたが、残りの団員をどうするかが、思案のしどころだった。』
『その団員を耕野村だけで収容しきれなかったのである。そこで八島考二氏の私有地を開放し入植させたが、残りの団員をどうするかが、思案のしどころだった。』
次回に続く…
▼こちらもよろしくお願いします▼


ちなみに紺色の部分は僕の勝手な補足です。
 『耕野(こうや)村とは、現在の伊具郡丸森町耕野である。』
『耕野(こうや)村とは、現在の伊具郡丸森町耕野である。』耕野に親戚がいるんで、以前行った事があります。阿武隈川と山に挟まれた風光明媚な所です。タケノコが美味しかったですね。
 『当時の耕野村の村長の任にあった八島考二氏は、狭い耕野村から満州への分村を考えていた。』
『当時の耕野村の村長の任にあった八島考二氏は、狭い耕野村から満州への分村を考えていた。』満州へ移民は人口増加や農地不足等の諸問題を解決しようとする政府の国策によって強力に推進されました。
村を分けるような形で集団移民する「分村」が耕野村でも計画されました。
 『なぜならこの地域には三反百姓が多く、次男、三男の働き口がなく、一家でも食うに足りないという有様だったからである。』
『なぜならこの地域には三反百姓が多く、次男、三男の働き口がなく、一家でも食うに足りないという有様だったからである。』まさにウチの母方の祖父はこの耕野村出身で次男でした。そして、満州開拓にも行きました。
 『満州へ移民団を送るには、団長の資格を有した者が必要であるなど、問題も多かったが、何とか解決を図り、次々と満州へ開拓団を送り出した。』
『満州へ移民団を送るには、団長の資格を有した者が必要であるなど、問題も多かったが、何とか解決を図り、次々と満州へ開拓団を送り出した。』団長になるのには幹部訓練を受ける必要がありました。昭和15年、耕野村より第一次開拓団20名が先遣隊として渡満。17年に栗原郡文字村(現栗原市)の14名と一緒に第二次開拓団が渡満。この時の団長は駒の湯温泉の経営者・菅原兵三郎氏を父に持つ菅原兵市氏でした。
 『開拓団の戸数も百戸を超えた。』
『開拓団の戸数も百戸を超えた。』満州は食べ物が豊富だったらしいです。しかも満州では、満州人が開墾した所にそのまま入植し、開墾するのでもトラクターなど機械が使えたようです。
 『しかし、昭和20年敗戦となり、それとともに第二の故郷を捨て、帰国せざる負えなくなってしまった。ところが、帰国はしたものの行き場所がなかった。』
『しかし、昭和20年敗戦となり、それとともに第二の故郷を捨て、帰国せざる負えなくなってしまった。ところが、帰国はしたものの行き場所がなかった。』ソ連の突然の侵攻により、命からがら日本に戻ってきます。その途中で多くの団員を失います。
映像では触れられていませんが、実際に引揚げ時の体験談を聞くと涙が止まりません。
 『その団員を耕野村だけで収容しきれなかったのである。そこで八島考二氏の私有地を開放し入植させたが、残りの団員をどうするかが、思案のしどころだった。』
『その団員を耕野村だけで収容しきれなかったのである。そこで八島考二氏の私有地を開放し入植させたが、残りの団員をどうするかが、思案のしどころだった。』次回に続く…
▼こちらもよろしくお願いします▼
2009年01月19日
「風雪とともに 開拓地耕英」を観る(第1回)
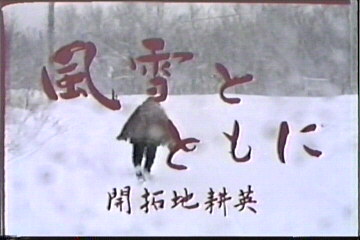
「風雪とともに 開拓地耕英(1993年度制作)」は栗駒山麓にある耕英の開拓の歴史と産業、厳しい大自然に挑んできた人々の暮らしにスポットをあてた映像作品で、郷土学習に使われる視覚教材のようです。
耕英地区には、1985年に栗駒小学校耕英分校の父母教師会が発行した、同名の開拓史があります。
今回、この「風雪とともに 開拓地耕英」を初めて観ましたが、開拓史「風雪とともに」をベースに、わかりやすく簡潔にまとめられた良い作品だと思いました。
耕英地区は戦後の開拓によって、誕生しました。
何もないブナの原生林から、人が暮らす現在のような姿になるまでは、厳しい自然条件と戦いながら開拓した、人々の叡智と努力がありました。
そうして築き上げてきた土地や産業が、岩手・宮城内陸地震によって、一瞬のうちに崩壊してしまいます。
時代背景や状況はもちろん異なりますが、開拓と地震からの復興は似ているのではないかと思います。開拓の歴史には、どこか復興へつながるヒントがあるかもしれません。
少しずつですが、紹介していきます。
ちなみに紺色の部分は僕の勝手な補足です。
 『宮城県西北部、栗駒山麓。真冬になると、このあたりは最低気温マイナス18度、積雪も多いところで2メートルにもなる厳寒の地である。』
『宮城県西北部、栗駒山麓。真冬になると、このあたりは最低気温マイナス18度、積雪も多いところで2メートルにもなる厳寒の地である。』『この地を自らの手で切り開いた人達がいたのだ。なぜ、このような厳しい寒さの地の荒れた土地に入植し、開拓しなければならなかったのだろうか…』
 『栗駒山中腹にある小さな分校、栗駒小学校耕英分校。』
『栗駒山中腹にある小さな分校、栗駒小学校耕英分校。』僕の母校ですね。
 『今日は勤労感謝祭の日である。』
『今日は勤労感謝祭の日である。』ソーラン節踊っています。
勤労感謝祭は地区の方を招待する行事で、出し物をします。学校に自分の子供・孫がいなくても、地区のほとんどの人が集まります。
ここは「婦人ホーム」という部屋で、小さい体育館のような施設です。
 そして、必ず餅をつきます。
そして、必ず餅をつきます。 宮城県は餅どころと言われるほど、事ある毎に餅を食べる習慣があり、種類も豊富です。例えば「ずんだ餅」は有名ですよね!
宮城県は餅どころと言われるほど、事ある毎に餅を食べる習慣があり、種類も豊富です。例えば「ずんだ餅」は有名ですよね!奥は雑煮。手前は餅に茹でた沼えびをからめた「えび餅」なんですが、口の中でえびが刺さって、痛かった記憶があります。
餅を食べながら、当時の思い出話に花が咲きます。
 『大槻好さん、67歳。耕英開拓者の一人である。』
『大槻好さん、67歳。耕英開拓者の一人である。』『えーあの頃はねぇ、ずいぶんと大変だったのっしゃ。開拓の歩みを語る前に、どうしてもやはり昭和15年くらいまで戻って、満州開拓の事言わないと、この開拓の誕生は出てこないのでがす。』
満州とは現在の中国東北部の事で、事実上、日本の傀儡国家とされている「満州国」がありました。
『昭和15年、耕野村の八島考二っあんという村長さんがね…』
次回に続く…
▼こちらもよろしくお願いします▼
2009年01月18日
河北新報で紹介されました!


1月18日付の河北新報朝刊ならびに河北新報社が運営するニュースサイト「コルネット」において、このブログでも製作状況をお伝えしていた「被災地ジオラマ」の記事が掲載されました。
記事: 崩落現場ジオラマに 栗原・耕英出身の金沢さん製作
宮城県で新聞と言えば河北新報。宮城で最も読まれている新聞に記事が掲載され、我々の取り組みを多くの方に知っていただける事は、大変喜ばしく思います。
記事の通り、このジオラマは栗原市耕英地区の住民組織「くりこま耕英震災復興の会」の若手グループ“Team Bikki(チーム・ビッキ)”の発案によるものです。
そのメンバーから依頼され、昨年秋より製作を始めましたが、このブログでは製作過程を紹介していました。これは栗駒に住むメンバーに進捗状況を伝える為でもありました。
ジオラマはあくまでも「被災状況を伝える」ツールです。
これから最大限に活用し、復興に向けた活動をしていきたいと考えています。
▼こちらもよろしくお願いします▼
2009年01月17日
阪神大震災の日に思う事

岩手・宮城内陸地震の最大の被災地・駒の湯温泉。尊い人命とともに開拓の原点を失った。
14年前の今日、「阪神・淡路大震災」が発生しました。
朝、起きて「関西って地震起こるんだ?」ぐらいの感覚でテレビを付けたら、ビルや高速道路は倒壊し、建物は火災によって燃えている映像が映し出されていました。それを観た瞬間、強い恐怖感に襲われたのを覚えています。
それから13年後、今度は私の故郷で、岩手・宮城内陸地震が発生します。
やはり最初、「何で栗駒の山ん中で地震なんか起こるんだ?」と…
神戸のような大都市と栗原市耕英とでは、人口も規模も産業も違います。
しかし、地震が起こったという事実には変わりなく、被災者の受けた苦しみも、そんなに違いはないと思います。
大地震はいつどこで起こるか、わかりません。
日頃から、大地震が起こった時に被害を最小に抑える努力や心構えをしておく事が重要です。
その為にも、今回の地震の記憶を風化させてはいけないと改めて感じました。
▼こちらもよろしくお願いします▼
2009年01月14日
ジオラマとイケメン

東京に戻ってきました。
本来の目的は、帰省を兼ねた栗原市栗駒までの完成したジオラマの運搬と住民組織「くりこま耕英震災復興の会」への引き渡しでしたが、他にも様々な出来事がありました。 詳しくは追々お伝えできればと思います。
さて、ジオラマの今後の展開については、
・製作範囲を拡げる(別の場所を作る)。
・同じ地点の被災前と被災後を作り、比較できるようにする。
という事で、意見が一致しました。
今後、イベント時や観光施設での展示が考えられます。しかし、近い内に参加するイベントの予定が無く、耕英地区の観光施設も営業できない状態なので、すぐに一般の方へお見せできる機会がなく残念です。何処かで公開が決まり次第、こちらでもお伝えします。よろしくお願いします。

今回、仮設住宅に隣接する談話室にお邪魔しました。
ここは住民達がミーティングや作業をする共有スペースになっています。
壁には全国の皆様から贈られた励ましのメッセージや被災現場の写真などが貼られています。
その一角に、地震関連の新聞報道がまとめられた切り抜きファイルがあったんですが、それらを見ながら地震の体験談なんか聞いていると、ある記事を発見しました!「狩野英孝さんが栗原市に応援メッセージを送った」って感じの記事です。(地元では話題になったの??)
狩野英孝さんとは、ご存知のとおり「ラーメン、つけめん、僕イケメン」でおなじみのお笑いタレント。実家は同じ栗駒の「櫻田山神社」っていうのは有名ですよね。

帰りに何となく、JR東北新幹線くりこま高原駅内にある栗原市の「田園観光課」を覗いたら、彼なりの熱いメッセージが入ったポスターが、入口のドアに貼っていました!
“どんな時でも、我々栗原市市民の気持ちを1つにすれば「効果テキメン、ボクイケメンで」頑張りましょう!”と(笑)
ちなみに栗原市公式ウェブサイトの栗原市の概要という所で紹介されている、郷土の有名人の項目には、現時点で「狩野英孝」という名前はありません。単に入れ忘れているだけなのか、あえて入れていないのか…
あと、栗原青年会議所が企画した「新生(みあ)れ!栗原プロジェクト」では、復興シールを作成し、購入していただいた売上金を義援金として活用しているそうです。 シールを作成には、栗原にゆかりのある宮藤官九郎さん(若柳出身)、高橋ジョージ(栗駒出身)・三船美佳さん夫妻、リリー・フランキーさん(映画ロケ地繋がり?)がご協力したそうなんですが、そこにも彼の名前は…
それぞれ色々な事情があるとは思われますが、どんなカタチでも、僕のような一般人がやるのと活躍されている有名人がやるのでは、影響力が違います。
どんどんアピールしていただく事によって、復興にも「効果テキメン」となればイイですね!応援しています!
▼こちらもよろしくお願いします▼
2009年01月11日
被災地ジオラマ製作(最終回)

だいぶご無沙汰してしまっているジオラマ製作ですが、そろそろ仕上げなくてはなりません。高い完成度を求めればきりがないのですが、一先ずこの辺で完成とします。
出来上がりはこんな感じです。

【実際の状況】

【ジオラマ】

【実際の状況】

【ジオラマ】

【実際の状況】

【ジオラマ】

ブログではサクサク製作が進んでいるかのように見えていたと思いますが、実際は試行錯誤の連続でした。しかし、そのおかげで、簡単に、材料費も抑えて作るコツがわかったような気がします。
本日、このジオラマを持って、栗原市栗駒に行ってきます。そしてジオラマの今後の展開についても話し合いたいと思っています。
▼こちらもよろしくお願いします▼
2009年01月02日
新年のごあいさつ

遅れ馳せながら、明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
昨年は様々な出来事がありましたが、やはり「岩手・宮城内陸地震」を抜きには語れない一年というか半年でした。
僕自身、あの地震がなければ、自分が育った耕英という地区について、よく考える事はありませんでしたし、この「栗おやじ」も生まれなかったでしょう。
本日、一関市という岩手県の最南端にあるに街に行ってきます。
一関は、僕が中学・高校時代を過ごした所でもあります。
そこである行事?に出席し、中学時代の友人たちと再会します。
▼こちらもよろしくお願いします▼